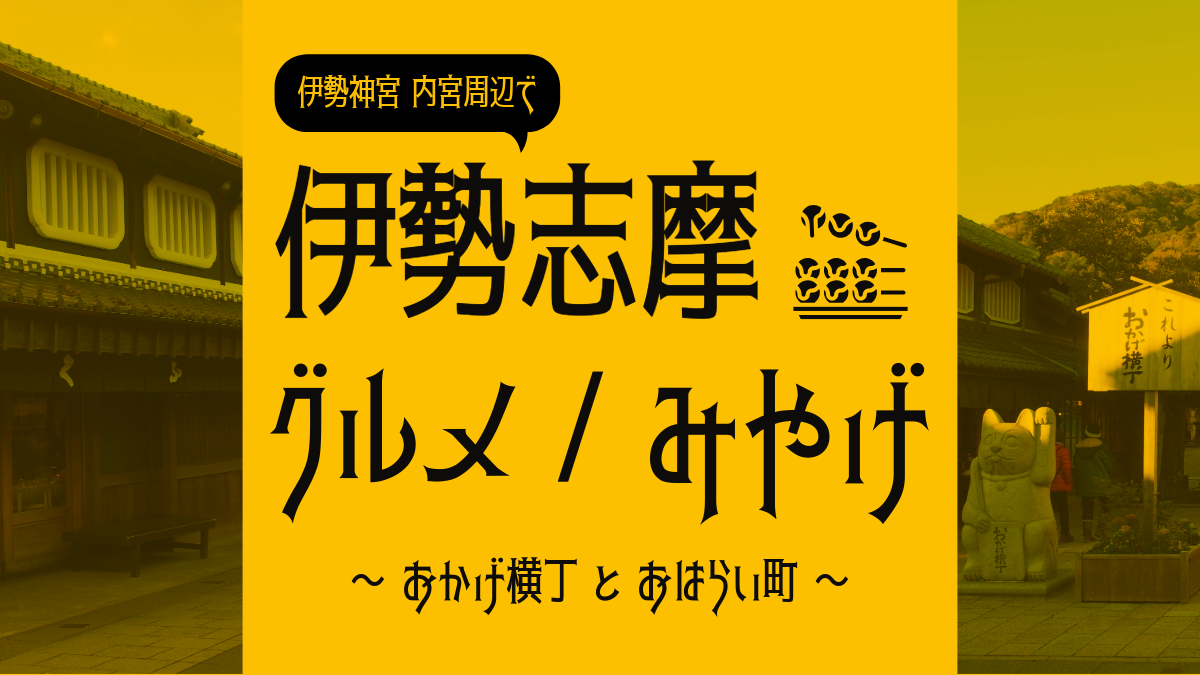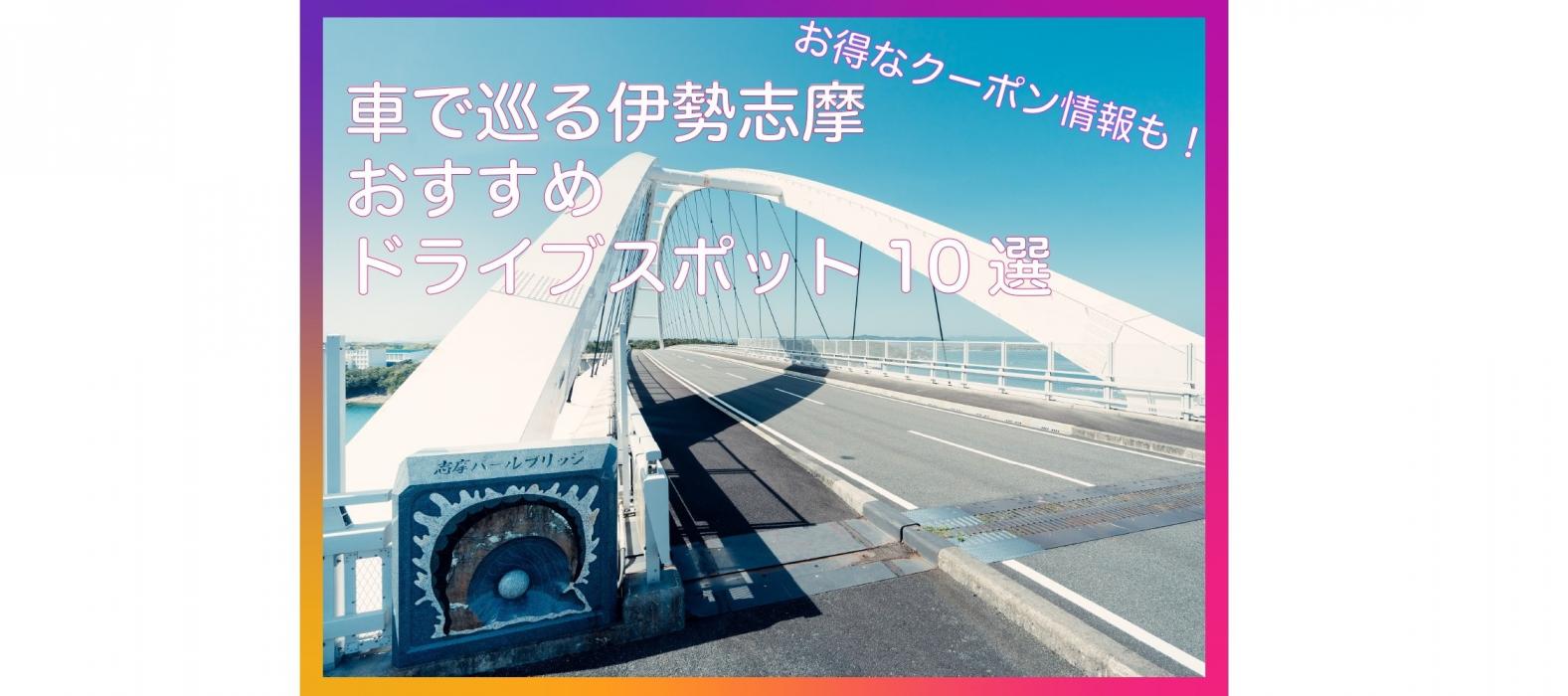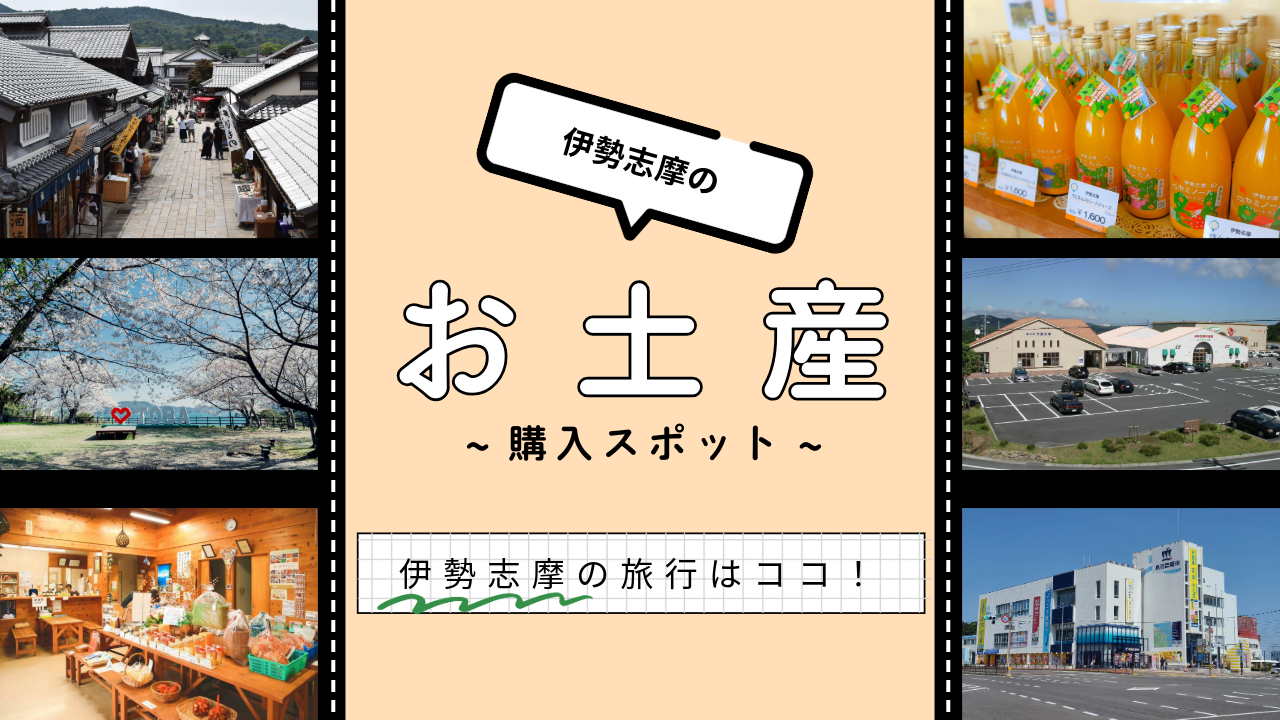御朱印すぽっと伊勢志摩
「御朱印」とは、お経を書き写してお寺に納めたとき、その証にいただくもの。
それがいつしか、参拝の証としていただけるようになり、御朱印集めを目的とした、寺社めぐりが浸透しました。
ところが最近は、「御朱印」集めの旅が女性の間で大ブーム。御朱印を集める専用の「御朱印帳」もおしゃれなデザインのものが多く、旅の思い出に最適!
アナタもでかけてみませんか?
鳥羽市の御朱印スポット

神明神社(石神さん)
女性の願いをかなえる女神様!もっと見る
相差(おうさつ)の森に静かに佇む地元の氏神、神明神社。その参道の途中の小さな社に祀られているのが「石神さん」です。相差は三重県内で最も海女が多い地域。その海女さんたちが古くから、「女性の願いなら必ず一つは叶えてくれる女神さま」と信仰してきました。
石神さんの御朱印はなんと朱色ではなくて紫色なんです。これはイボニシ貝から採った「貝紫」という色なんだとか。他ではいただけない御朱印を是非ゲットしてください。
お参りの後には、海女さんたちが身につける魔よけの印「ドーマンセーマン」が描かれた二つのお守りのチェックもお忘れなく!
青峯山正福寺
もっと見る海で働く人が信仰するお寺です
標高336mの青峯山(あおのみねさん)山頂にある広大な寺院です。
本尊の十一面観音菩薩は、相差の海からクジラに乗り現れたと伝わり、乗ってきた鯨は龍宮池の鯨石になったという伝説があります。
入口にそびえる大門には鳳凰や龍など様々な彫刻が施され、江戸時代に「鳥羽藩に過ぎたるものの一つ」と俗謡に唄われたほどで必見です。
また、このお寺は、漁業や船舶関係者の信仰が厚く、旧暦1月18日には「御船祭」が行われることでも有名です。
志摩市の御朱印スポット

宇賀多神社
もっと見る試験と勝負にご利益アリ!
主祭神として祀られている五男三女神のうち「天忍穂耳命(あめのおしほみみのみこと)」が勝利の神であることから、勝負ごとにご利益のある神社として知られています。
「宇賀多」は「受かった!」、「うっ勝った!」に通じるということから、多くの受験生やスポーツ選手が参拝に訪れます。
また境内には、雷から本殿を守った「なぎの木」があり、その木の葉が災難よけのお守りになっています。
大慈寺
もっと見る花も観賞、「志摩のあじさい寺」
九鬼水軍波切丸の大将川面右近とその臣下の強者(つわもの)がひっそり眠る大慈寺。
6月には、境内に1500株のあじさいが咲き乱ることから「志摩のあじさい寺」と呼ばれています。
また、2月中旬には、「てんれい桜(河津桜)」が咲き、これらの頃は、あたかも花極楽になります。
伊雑宮
もっと見る伊勢神宮内宮の別宮
古代から「志摩一の宮」と称され、格式高いといわれるお宮。
地元では「イゾウグウ」、「イソベさん」と呼ばれています。
ご祭神は、天照大御神御魂。境内にある大楠は、その形から「巾着楠」と呼ばれ親しまれています。
伊雑宮の御田植式(毎年6月24日)は志摩地方第一の大祭で、一般に「御神田(おみた)」といわれ、国の重要無形民俗文化財に指定。
度会町の御朱印スポット

国束寺
もっと見る心身が癒される自然に囲まれたお寺 度会町の豊かな自然の中にひっそりと佇む山寺です。
国束山頂に聖徳太子の命により建立されたのが始まりとされ、かつては伊勢・朝熊の金剛證寺と並ぶ南伊勢の名刹として栄えました。
戦後、一部を大阪の四天王寺に移したうえで、国束山麓の平生に移築し、現在に至っています。
それぞれにご利益が異なるいろんなお守りがあり、玄関外側に貼って厄病を退ける魔除けの護符は昔から伝わるものとして知られています。
南伊勢町の御朱印スポット

仙宮神社
もっと見る外宮とも関わりが深い由緒ある神社
「猿田彦神社」の祭神としても知られる猿田彦命(さるたひこのみこと)を祀り、伊勢神宮の外宮とも関わりが深い由緒ある神社です。
標高約70mの山の上のにあり、裏手の磐山には、猿の横顔のに似た巨岩を見ることができます。
絵馬殿には百人一首や天の岩戸の神話にちなむ色鮮やかな絵画が奉納されており見ごたえ満点。
本殿背後には古代の祭祀跡もあります。
~番外編~東京大神宮
神前結婚式創始の神社
明治13年(1880)、伊勢神宮の遥拝殿として創建されました。「東京のお伊勢さま」といわれ親しまれており、伊勢神宮の内宮と外宮のご祭神である天照皇大神と豊受大神が祀られています。
さらに万物の〝結び〟の働きを司る「造化の三神」が祀られていることから、縁結びにご利益がある神社としても知られており、良縁を願う人々が全国各地からお参りに訪れます。現在広く行われている神前結婚式は、東京大神宮が創始とのこと。今もご神前で伝統的な結婚の儀式を守り伝えているそうです。